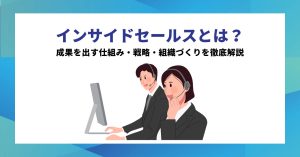営業代行はやめとけ?失敗する企業と成果を出す企業の違い
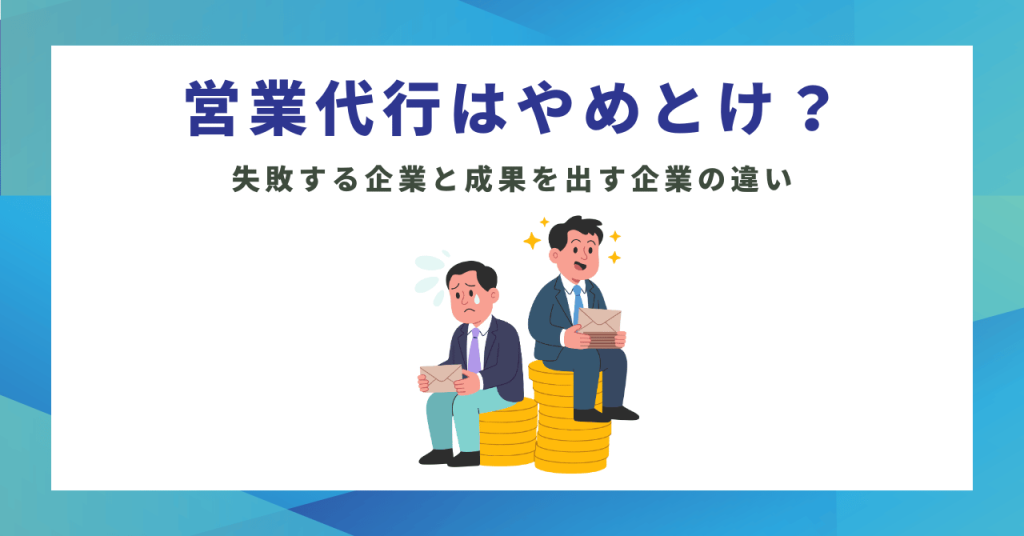
「営業代行はやめとけ」検索すると、そんな言葉が目に入ります。「丸投げしても成果が出ない」「人がすぐ辞める」「報告が雑だった」など、営業代行に対するネガティブな口コミは少なくありません。
しかし、現場を知る僕の目線では、それは営業代行という仕組み自体の問題ではなく、“使い方”の問題です。実際、営業代行をうまく活用する企業は多く存在します。
営業代行が「やめとけ」と言われる背景には、いくつかの構造的な誤解があります。
本記事では、
- なぜ営業代行が失敗しやすいのか
- どんな商材なら成果が出やすいのか
- 成功している企業が共通して行っていること
を、営業現場の視点から具体的に解説していきます。
営業代行が「やめとけ」と言われる背景
営業代行という言葉が広く知られるようになったのは、ここ10年ほどのことです。
もともとは、テレアポや訪問営業を請け負う“アポイント獲得代行”のイメージが強く、「電話をかけまくってアポを取る会社」という認識が根づいていたかと思います。
この頃は、成果報酬型の低単価モデルが流行した影響で、
- 案件ごとの理解が浅いまま電話をしていた
- 担当者が短期間で入れ替わる
- アポの質が低く、受注につながらない
といったトラブルが頻発。
その結果、「営業代行=リスクが高い」「やめておけ」というイメージが強まった印象があります。
現在の営業代行はまったく別物
ここ数年で、営業代行業界は大きく進化しています。もはや「アポを取るだけ」の単機能型企業は少数派で、戦略設計からリード獲得・商談化・クロージング・分析改善までを一気通貫で支援するハイブリッド型が主流になっています。
実際に、過去に僕自身が営業フリーランスとして参画していた営業代行会社でも、クライアントと一体化しながら戦略立案・改善提案までを行うケースが増えています。
「営業を請け負う」のではなく、「成果を共に設計していく」という考え方が、確実に広がっていると感じます。
多くの営業代行会社が「アポイントを取る」ではなく「顧客の営業成果を一緒に実現する」ことを目的に、チーム体制・データ分析・ナレッジ共有を仕組み化しています。
| 支援領域 | 主な役割 | 目的 |
| 戦略・設計 | ターゲット選定、訴求整理、KPI設計 | 成果が出る“営業の型”を作る |
| インサイドセールス | 架電・メール・SNSでの接点創出 | 見込み顧客の育成と検証 |
| フィールドセールス | 商談・提案・クロージング | 受注・契約の最大化 |
| データ分析・改善 | 商談データの分析・トーク改善 | 再現性のある営業活動へ |
このように、今の営業代行は“営業の一部を代わりにやる会社”ではなく、顧客企業とともに営業体制そのものを磨き上げていく共創パートナーへと進化しています。
「営業代行は成果が出せない」という誤解が残る理由
それでもなお、「営業代行=テレアポ会社」という昔のイメージは根強く残っています。
実際、ネットで「営業代行」と検索しても、出てくるのは数年前の体験談がほとんどです。
そのため、古い失敗例だけが独り歩きしているのが実情です。「丸投げしても成果が出ない」「担当者がすぐ辞める」といった声は、当時の構造のまま語られているケースが多い。
今の営業代行は、仕組みも人の関わり方も大きく変わっています。クライアントと並走しながら成果をつくる共創型の支援だからこそ、僕自身も営業支援という仕事の本質的な価値を実感しています。
営業代行で失敗する企業の共通点
営業代行を導入する企業は年々増えていますが、すべての企業がすぐに成果を出せているわけではありません。
サービスによって営業代行の質に差はありますが、成果を分ける最大の要因は、依頼の仕方や体制設計にあります。
僕自身、これまで多くの企業の営業支援に携わるなかで、「営業代行が合う・合わない」という単純な話ではなく、“どう関わるか”・“どう仕組みを作るか”によって成果はまったく変わると実感しています。
ここでは、そうした“成果が出づらくなるパターン”を整理し、逆に言えば「ここを押さえれば成果が出る」ポイントをお伝えします。
「売ること」だけを期待して丸投げしている
営業代行を「売ってくれる会社」として扱ってしまうケースです。
多くの企業は、戦略やターゲットをしっかり整理しています。
ただ、その情報を共有して終わりにしてしまうことがよくあります。
たとえば、ペルソナや営業トークをマニュアル化して渡しても、その後の反応やフィードバックを代行と一緒に検証できなければ、現場の知見は活かされません。結果として、代行側が「指示された内容を再現するだけ」になってしまい、成果も限定的になります。
とはいえ、日々の業務の中で頻繁にミーティングや振り返りを行うのは現実的ではありません。担当者の負担が増えると「それなら自社でやった方が早い」と感じてしまうのも当たり前ですよね。
だからこそ、僕は“共創”を仕組みとして機能させることが大切だと考えています。
たとえば、
- 商談ログを共有し、会議を増やさずにデータで振り返れるようにする
- KPIや進捗を可視化し、コメントだけで意思疎通できるようにする
- 改善提案や検証は代行側が主導し、担当者は意思決定に集中する
実際、MUSUBIでもこの設計を意識しており、効果検証や改善提案は営業代行側で主導的に行うことで、クライアントの工数を最小化しています。
「まかせて終わり」ではなく、「まかせて成果と余白を生む」状態をつくるという考え方です。
成果の定義があいまい
「アポ」「商談」「受注」どこを成果とするかを最初に決めていないと、 営業代行と企業側で評価の軸がズレていきます。たとえば代行側は「商談数をKPIとして達成」と報告していても、企業側は「売上が伸びていない」と感じる。
この状態では、どちらも“やっているのに報われない”関係になります。
成果を数字で分解して、責任範囲を明確にする
営業代行を活かすうえで大切なのは、成果の“共通指標”を数字で定義しておくことです。
MUSUBIでは、以下のように整理してスタートします。
| 指標 | 意味 | 主な責任範囲 |
| KGI | 売上・受注など最終成果 | クライアント側 |
| KPI① | 商談獲得数・アポ率 | 営業代行側 |
| KPI② | 提案通過率・受注率 | 双方で分析・改善 |
「どの指標を誰が追うのか」「どの数字を見て改善するのか」を明確にしておくことで、
報告のための数値ではなく、次の一手を決めるための材料になります。
すり合わせは手間ではなく、ムダを減らすための仕組み
初期のすり合わせを面倒に感じる方もいるかもしれませんが、ここを曖昧にしたまま始めると、あとから認識のズレを修正するほうがずっと大変です。
実際、MUSUBIでも最初の1〜2回の打ち合わせで指標設計を固めることで、その後の報告・改善の工数を大きく減らせています。
成果の定義を明確にすることは 「成果をどう見るか」を一致させるための最初の設計です。これができていれば、営業代行は動いて終わる存在ではなく、数字を一緒に伸ばすパートナーとして機能します。
短期間での結果を求めすぎる
僕は、営業代行の本質、売ることではなく、顧客とその先の顧客を成功させることだと考えています。営業とは単に商談や契約を増やす活動ではなく「どんな顧客が、どんな課題を抱え、どうすれば価値を感じてくれるのか」を解き明かすプロセスです。
そのための最初の1〜3ヶ月は、ターゲットや訴求、提案の方向性を検証しながら「誰に」「どんな切り口で」「どんな体験を提供するか」を具体的に磨いていきます。
たとえば、
- SaaS商材なら、導入後に現場でどう使われるかまで見据えた提案を行うことで、単なる比較検討ではなく“活用の未来像”を描けるようになる。
- 業務支援サービスなら、導入時の負担を最小化する運用設計を提示することで、決裁者だけでなく実務担当者の納得感を得られる。
こうした顧客の成功を設計する時間を省いて結果を急ぐと、目先の数値は動いても、再現性のある成果にはつながりません。
営業代行の成果とは、単なる契約件数ではなく、顧客が自社の価値を実感できる状態をどれだけ生み出せたかで測るべきものです。短期のスピードではなく、検証と改善を積み重ねる精度が大事です。
兆しが見えないときは、怖がらずに設計を見直そう
営業代行で成果が出ないときは、単に「時間が足りない」からではなく、ターゲット設定やリスト、トークの方向性にずれがある可能性があります。そして、それを判断するのに3ヶ月も待つ必要はありません。
一般的な営業体制があれば、仮説検証のサイクルは数日単位で回ります。リストの反応データを集計し、どんな層が商談化しやすいかを確認する。反応が高いトーク内容を即座にスクリプトへ反映する。
このように、検証と改善を日次で回せる体制であれば、1週間もあれば方向性の精度をある程度見極めることができます。
逆に、1か月経っても手応えがない場合は、運用の問題というより、検証の仕組みが機能していないと考えた方がいいでしょう。
たとえば、
- 想定した業界の反応率が想定を大きく下回っている
- 商談後のフィードバックが整理されず、改善が進まない
- 担当者の経験や感覚だけでトークが決まっている
こうした状態では、時間をかけても成果は出にくいです。営業代行を「動かす人手」としてではなく、検証を共に行い、改善を素早く反映できるパートナーとして活用できているかどうかが重要です。
MUSUBIでも、初期の段階から日次でデータを集約し、状況やヒアリング内容をもとに即座に仮説を修正しています。このように、運用の“回転数”を高めることで、 結果を早く、かつ安定的に積み上げることが可能になります。
商材によって「営業代行の向き・不向き」はある
営業代行はどんな商材にも万能なわけではありません。 同じ営業支援でも仕組みとして再現できる商材と個々の提案力や関係構築に左右される商材では、求められる関わり方がまったく違います。
つまり、営業代行が向いていない商材があるというよりも、活かし方の設計を間違えると成果が出にくい商材があるというのが正確です。
ここでは、営業代行と相性の良い商材の特徴、そして成果を出すために工夫が必要な商材について整理します。
営業代行に向いている商材の特徴
営業代行を導入して成果が出やすいのは、営業活動を“仕組み化”しやすい商材です。
つまり、「誰が」「どのように伝えても」価値が一貫して伝わる構造を持っている商材です。
| 商材タイプ | 特徴 | 成功要因 |
| SaaS・ITツール | 課題が明確で価値が定量化できる | トーク設計・KPI設計が型化できる |
| Webマーケ・制作・広告支援 | 成果指標(CVR、CPAなど)が具体的 | 数値で効果検証できるため改善サイクルが早い |
| コンサルティングサービス | 経営課題解決など提案型 | 営業人材が業界理解・仮説提案できる体制なら高相性 |
| 教育・研修・福利厚生 | 決裁者層が明確・比較検討しやすい | 汎用スクリプト+カスタマイズで成果が安定しやすい |
| サブスク・定額サービス | 導入後の継続利用でLTVが高い | リード獲得中心でもROIが取りやすい |
営業代行に向いている商材の特徴
営業代行が「苦手」なのではなく、商材の特性によってアプローチ設計が複雑になるケースがあります。
下の表では、そうした代表的な商材タイプと、難易度が上がる理由・対策の方向性をまとめています。
| 商材タイプ | 難易度が上がる理由 | 成果につなげるための対策 |
| 人材紹介・派遣 | 人材が案件ごとに異なり、トークの再現性が低い | 登録促進や初期接点(面談設定)までを代行範囲に限定し、案件単位の提案は自社側で対応する |
| 受託開発・オーダーメイド案件 | 案件ごとに課題・提案内容が変わり、打ち手の汎用化が難しい | 業界や課題別にシナリオを複数パターン化し、初期商談までは半自動化できる構造を作る |
| ローカルビジネス(店舗誘致・地域特化サービス) | リスト範囲や地理的な密度に制約があり、母数を確保しにくい | オンライン広告やSNS運用と組み合わせ、リード接点を増やすハイブリッド設計にする |
| 単価の低いBtoB商材 | 1件あたりの粗利が小さく、CPA(顧客獲得コスト)が逆転しやすい | 完全成果報酬よりも時間単価・月額固定型など、リスクの少ない契約設計を検討する |
| コンサル・抽象的サービス | 成果の定義が曖昧で、顧客課題の言語化に時間がかかる | 営業代行に「案件化」ではなく「仮説検証」を任せ、ニーズ層の見極めやメッセージ検証を優先する |
これらの商材でも「営業代行が合わない」のではなく、どこを外部に任せ、どこを自社で担うかを設計することで成果につなげることは充分に可能です。
代行を売り方を一緒に設計するチームとして活用することで、難易度の高い商材でも再現性を作ることができます。
成功する企業がやっている3つのこと
① 営業代行を事業戦略の一部としてとらえている
営業代行をリソース強化の手段として活用するのはとても合理的です。実際「新しいアプローチができて助かった」「営業の動きが止まらずに済んだ」と言っていただけることも多いです。
自社の人材を増やすよりも早く動ける。そのスピード感も営業代行の価値だと思います。
一方で、成果を出している企業はその速さをきっかけに、営業代行を事業の検証フェーズとして組み込むケースが増えているように実感しています。
どの市場が反応するか、どんな顧客層に手応えがあるかを一緒に見ながら、戦略そのものを磨いていく。
この使い方をすると、単なる外注ではなく、事業を加速させる仕組みとして機能します。
②数字を判断材料として使い倒している
成果を出す企業は、数字を結果として終わらせず、次の打ち手を考えるための材料として扱っています。営業では想定通りの成果だけでなく、反応が薄かったリストや断られた理由にも、多くのヒントがあります。
たとえば、反応が低かった業界は訴求を変えれば掘り起こせる可能性があるし、断られた理由の傾向から、新しい切り口が見えてくることもあります。
数字を“良い・悪い”で評価して終わるのではなく 「なぜそうなったか」を分解して使い切る。この姿勢を持つ企業は、代行と一緒に成果を積み上げるスピードが格段に速いです。
③ 成果を「一時的な数字」ではなく「再現性」で見る
数字を使い倒す姿勢の先にあるのが、再現性です。
単発の成果を評価するのではなく、同じ結果を何度でも生み出せる状態にする。
この視点を持つ企業は、代行を使うことで社内ナレッジが積み上がり、仕組みとしての営業力が強くなっていきます。
たとえば、
- どんな訴求が特定業界に刺さったか
- 商談でよく聞かれたキーワード
- 断られた理由の傾向
これらを定期的に整理し、マーケティングや次の営業に展開する。代行を「成果を出すための外注」ではなく、自社の学習プロセスを拡張する仕組みとして活用しているのが特徴です。
良い営業代行会社の見極め方【チェックリスト】
営業代行を「やめとけ」にしないためには、まかせて終わりにならない会社を選ぶことが何より大切です。 以下の5項目を確認すれば、実際に成果を出している代行会社かどうかを見極めやすくなります。
| 見極めポイント | 具体的な確認内容 | チェックの目安 |
| KPI設計力 | 目的に合った成果指標(例:商談数、成約率、LTVなど)を提案段階で明示できるか | ヒアリング時に「どんな数字を追うか」を逆提案してくれるかどうか |
| 報告・改善体制 | 単なるレポート提出ではなく、次の打ち手を含めた改善提案があるか | 週次・隔週で定例MTGを設定しているか、データを共有してくれるか |
| 営業人材の質 | トーク力よりも、業界理解・課題ヒアリング力があるか | 担当者の営業経験年数や過去案件の業界を具体的に聞いてみる |
| 契約モデル | 固定+成果報酬など、双方のリスクを分散できる設計か | 成果報酬のみを強調しすぎていないか(短期的運用のサイン) |
| コミュニケーション | 対応が早く、担当者の変更リスクが低いか | 連絡チャネル・稼働体制・担当継続率を確認する |
契約前の段階で「どこまで一緒に考えてくれるか」を見るのが最も確実です。営業代行は、提案内容そのものよりも、伴走姿勢と改善力に差が出ます。迷ったときは、“一緒に数字を作れる会社かどうか”を基準に選ぶと失敗しにくいです。
まとめ/「やめとけ」ではなく「どう使うか」
営業代行に対する「やめとけ」という声の多くは誤った使い方や設計の浅さから生まれた誤解です。営業代行は、万能ではありませんが、“正しく使えば確実に機能する仕組み”です。
成果を出している企業に共通しているのは、戦略・数値・関係性の3点を代行と共有していること。戦略で方向を合わせ、数値で現状を見て、関係性で継続的に磨いていく。
その積み重ねが、営業を“外注”から“共創”へと変えています。
営業代行は「売る人」ではなく、「売れる仕組みを一緒に動かす人」。
どう使うか次第で、成果の伸び方も、営業組織の未来も変わります。

成果が出る営業代行を検討中の方へ
MUSUBIでは、実際の営業活動を通じて得たデータをもとに、
成果につながる打ち手を一緒に磨いていく支援を行っています。
「まずは実働を任せてみたい」「今のやり方が正しいか確かめたい」など、
初期フェーズから気軽に相談できる体制を整えています。
営業代行を“任せて終わり”にしないための第一歩として、
ぜひ一度ご相談ください。