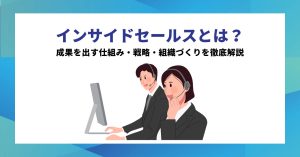商談とは?意味と流れを実例で解説|成果につなげる営業の基本
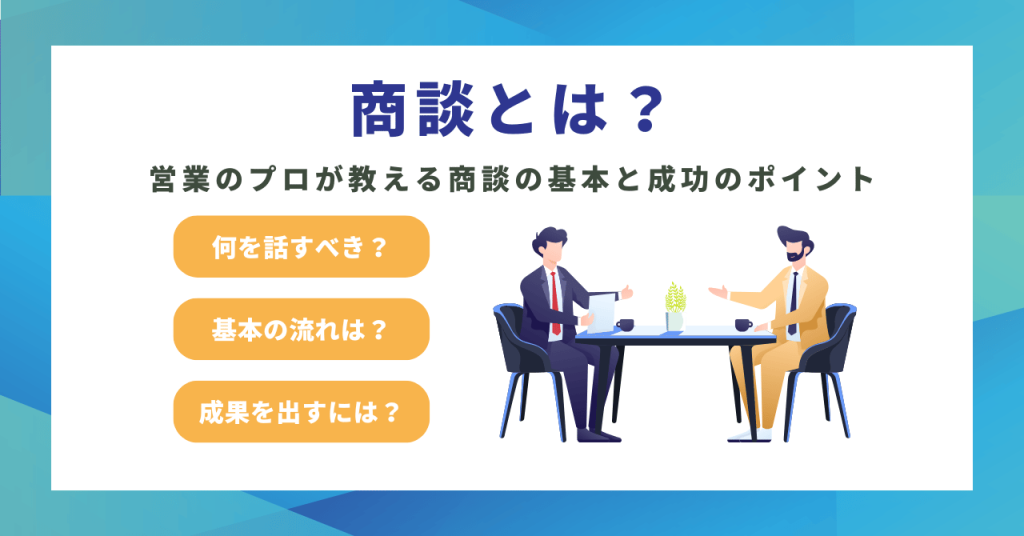
「商談」と聞くと、営業が商品を売り込む場というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、実際の商談は「話す場」ではなく、相手の課題を一緒に見つけ、解決の道筋をつくる場です。
特に、オンライン化や情報の非対称性が減った今、商談の本質は「売り込み」から「共創」に変わっています。どれだけ話が上手くても、相手の課題を正確に理解できなければ、成約にはつながりません。
本記事では、営業代行の現場で実際に成果を出してきた経験をもとに、初心者にもわかりやすく「商談とは何か」から「流れ」「成果を出すためのポイント」までを解説します。
この記事を読めば、なんとなく商談している状態から、成約率の上がる商談ができる営業へと変わるヒントが見つかるはずです。
商談とは?「売り込み」ではなく、意思決定を動かすプロセス
商談とは、商品やサービスの取引に関する交渉や相談を通じて、買い手の意思決定を支援するプロセスです。営業職にとって最も重要なビジネス機会です。
多くの人は商談を説明の場だと考えていますが、本質は、相手の課題を理解し、納得して意思決定できる状態をつくること。つまり、商談は売り込む行為ではなく、相手と課題を共有し、解決に向けて動くための対話です。
営業代行やBtoB営業の現場では、商談を次の三つの段階で整理しています。
- 商談前:アプローチ、リサーチ、仮説立て
- 商談中:ヒアリング、提案、クロージング
- 商談後:フォロー、関係構築、再提案
この流れを意識的に設計することで、商談は偶然の成約から再現性のある成果へと変わります。
商談の目的は売ることではなく「納得を作ること」
多くの営業が、商談を「説明の場」と捉えています。 しかし、相手が本当に求めているのは商品の機能ではなく 「自社の課題がどう変わるのか」「どんなリスクがあるのか」という納得の根拠です。
一方的なプレゼンでは信頼は生まれません。商談とは、話すよりも聴いて理解する時間。相手の背景や事情を深く理解して共感を示すことで、初めて課題を共有でき「この人なら任せたい」という感情が生まれます。
商談と「打ち合わせ」の違い
商談は意思決定を前進させるための対話。ゴール=「何を決めるか」を明確にして臨むものです。一方で打ち合わせは情報共有や作業調整。ゴールは決定ではなく確認です。
商談の流れ/前・中・後の3ステップを理解する
商談は、顧客との対話を通じて課題を明確にし、提案・契約・フォローへと進む流れで進行します。このプロセスを「商談前」「商談中」「商談後」の三つに分けて設計しておくことで、どの段階で課題が生じているかを明確にでき、成約率の改善につながります。
営業代行の現場でも、商談を感覚ではなくプロセスとして管理することで、成果の再現性を高めています。
商談前 ― 成功の8割は設計で決まる
商談前は、目的と進め方を整理し、商談全体を設計する時間です。準備=資料作成をイメージする人も多いかもしれませんが、本当に重要なのは相手を理解し、どんな結果を目指すかを明確にすることです。
商談前に整理すべき3つの要素
商談前のリサーチでは、外部情報だけでなく、インサイドセールスや過去接触データの情報も合わせて整理します。目的は、相手の状況や関心の方向性を具体的にイメージすることです。
主な情報源と確認ポイント
| 情報源 | 確認内容 | 狙い(目的) |
| 企業サイト・プレスリリース | 事業内容、サービスライン、直近の動き | 企業の方向性や注力事業を把握する |
| IR・決算情報 | 売上構成、注力領域、コスト増減など | 業績面から潜在的な課題や投資傾向を推測する |
| SNS(LinkedIn、Xなど) | 経営層や担当者の投稿内容、関心テーマ | 担当者の興味・関心や現在の課題意識を把握する |
| 過去の商談・問い合わせ履歴(インサイド情報) | 以前の提案内容、反応、懸念点、問い合わせ経路、決裁フロー | 検討経緯や関係性を再確認し、会話の焦点を定める |
| 自社のCRM/SFAデータ | 商談前後の行動ログ、やり取り頻度、検討フェーズの位置付け | 温度感や進捗状況を定量的に把握する |
これらを整理して 「どんな課題を抱えていそうか」「今回の商談で何を確かめるべきか」を1枚の商談設計シートとしてまとめておくと、ヒアリングが格段に精度を増します。
営業代行の現場では、この設計シートを毎回インサイドチームと共有し、事前に聞くべきポイントをすり合わせてから商談に臨むのが基本です。
商談前の準備①ゴールを設定する
商談前には、この時間で何を決めるかを必ず定義します。
目的が曖昧なまま商談に入ると、どれだけ話が盛り上がっても「良い話だった」で終わります。
たとえば次のように、フェーズごとにゴールを設定しておくと明確です。
| 商談のフェーズ | 主な目的 | ゴール設定の例 |
|---|---|---|
| 初回商談 | 相手の現状把握、課題の抽出 | 「現状と課題を整理し、次回提案の方向性を合意する」 |
| 提案商談 | 課題への解決策提示、意思決定支援 | 「提案内容を評価いただき、導入の検討基準を明確にする」 |
| クロージング商談 | 契約条件・導入時期の合意 | 「導入スケジュールと契約プロセスを確定する」 |
営業代行の現場では、商談1件ごとにゴールメモを作成し、チーム全体で「今回は何を決める場か」を共有してから臨みます。これにより、商談の目的がズレず、次のステップに確実に進めるようになります。
商談前の準備②アジェンダを共有する
商談前、または冒頭で「今日の目的と流れ」を共有しておくと、相手の不安が減り、会話が整理されます。とくにオンライン商談では、冒頭1分の印象が商談全体のリズムを決めます。
共有の際は、以下の流れで話すとスムーズです。
| 項目 | 例文・活用例 |
| 開始時の導入 | 「本日は30分ほどで、現状の課題と今後の提案方向について確認させてください」 |
| 流れの提示 | 「前半15分でヒアリング、後半で提案概要を共有し、最後に次のステップを相談できればと思います」 |
| 所要時間 | 「全体で30分を想定していますが、延長が必要な場合はお知らせください」 |
| ゴールの明示 | 「今日のゴールは、課題と提案の方向性をすり合わせることです」 |
営業代行チームでは、商談スライドの1枚目をアジェンダ専用スライドに固定しておくケースが多いです。これにより、初対面でも商談の全体像が共有でき、相手が安心して会話に集中できます。
商談前の準備③情報を集めるより焦点を合わせて話す
情報量を増やすことよりも、相手の状況に対して何を話すかを決めることが大切です。自社の強みを並べるより、相手の課題にどの強みが最も響くかを整理しておく。
この「焦点を合わせる」作業ができているかどうかで、商談の成功率は大きく変わります。
商談中 ― 信頼を築き、課題を共に発見する
商談中は、相手と信頼関係を築きながら、課題を明確にし、解決の方向性を共有する段階です。繰り返しになりますが、商談の目的は商品を説明することではなく、相手が抱えている課題を一緒に整理し、納得できる道筋を描くことです。
商談でやること①アイスブレイクと目的共有
初対面の商談では、いきなり本題に入らず、短い雑談や軽い質問から入るとよいです。
「このたびはご時間ありがとうございます。今日は◯◯の件で20分ほど、お話を伺えればと思います」といった形で、商談の目的と時間を共有してから本題に入ります。
この最初の1分で、相手の緊張を解き、信頼の土台をつくることができます。
商談でやること②ヒアリング/現状・課題・理想を聞く
商談の中心はヒアリングです。「何に困っているか」よりも「なぜそうなっているか」を掘り下げて聞くことで、真の課題が見えてきます。
とはいえ、唐突に「課題を教えてください」といっても答えづらいものです。
以下のように、現状・理想・理想の実現における障壁の3段階で質問するとスムーズです。
- 現状:「いまどんな体制で運用されていますか?」
- 理想:「理想的な状態はどんな形でしょうか?」
- 障壁:「それを実現するうえで、どんな課題が一番大きいですか?」
一度に全部を聞こうとせず、会話の流れに沿って自然に出してもらうのがポイントです。
相手の発言を遮らず、要点をメモしながら共感を返すだけでも、相手の安心感は大きく変わります。
商談でやること③提案/課題解決の筋道を示す
ヒアリングで得た情報をもとに、課題をどう解決できるかを整理して伝えます。
このとき重要なのは、機能や価格ではなく、「課題→解決→期待される効果」の順で説明することです。
たとえば、「営業リソースが限られているとのことでしたので、まず商談獲得までを自動化する体制を一緒につくる形でご提案します。」といったように、相手の言葉を引用しながら話すと、納得感が高まります。
商談でやること④クロージングと次のアクション設定
商談の最後に、次のアクションを自分から提案して明確にします。
たとえば「来週中にこちらから提案資料をお送りします」や「次回は導入スケジュールを中心にお話しさせてください」など、
営業側が主導して次の動きを提示することで、商談が途切れません。また、商談を終える際は、要点をまとめて口頭で確認しておくと誤解が防げます。「今日は課題の整理までを行い、次回は具体的な提案書をベースにお話しする、という形で進めますね。」とまとめるとよいでしょう。
商談後 ― フォローが次の商談をつくる
商談後は、結果がどうであれ、次の接点につなげる最も重要なフェーズです。
クロージングに至らなかった場合でも、商談を一度きりで終わらせない仕組みを持つことで、長期的な成果が生まれます。
商談後のフォロー①商談直後のフォローメール
商談が終わった直後、できれば24時間以内にフォローメールを送ります。
内容はシンプルに、
- お礼
- 商談の要点(合意した内容・保留事項)
- 次のアクション(担当・期限)
の3点を明確に記載すること。
【フォローメールの例】
件名:本日の打ち合わせお礼/次回のご提案について
本日はお時間をいただきありがとうございました。
商談では、◯◯の課題と今後の方向性について以下の内容を確認いたしました。
- 現状課題:〇〇
- 次回検討事項:〇〇
次回は〇日までに資料をお送りしますので、ご確認をお願いいたします。
このように、要点を整理して送ることで、記録としても残り、社内共有もスムーズになります。
商談後のフォロー②CRMでの記録と共有
フォロー後は、商談内容をCRMやスプレッドシートに記録します。特に重要なのは「感触(温度感)」と「決裁プロセス」の2点です。これが残っていないと、次回以降の商談設計が毎回ゼロからになります。
営業代行の現場では、
- 感触を「A(導入前向き)」「B(要再提案)」「C(検討見送り)」などで分類
- 決裁者・関係者・稟議フローをメモ化
しておき、再提案時に過去情報を即参照できるようにしています。
商談後のフォロー③関係を切らさないアプローチ
フォローの本質は関係をつなぐことです。 商談が終わったあとも、
- 新しい導入事例
- 関連ニュース
- セミナーや資料提供
などを定期的に共有することで、相手の検討モードが戻ったタイミングで再接触できます。
また、失注した案件はリスト化してリマインドを入れることが重要です。「3か月後に再連絡」「新サービス公開時に再提案」など、CRM上でリマインダーを設定しておくと、抜け漏れが防げます。
商談後の対応を丁寧に行えば、失注案件が将来の受注案件に変わります。成果を出す営業は、商談を終わらせず、常に次のきっかけを仕込んでいます。
商談を成功に導くポイント
商談を成功させるには、流れを覚えるだけでなく、各段階でどのように相手の納得をつくるかを意識することが大切です。
ここでは、商談の前・中・後それぞれで成果を左右するポイントを整理します。
商談前:相手を深く理解する
商談の前段階で、どれだけ相手の状況を深く理解できているかが、その後の展開を決めます。
単に「事業内容を調べた」では不十分で、課題仮説と商談のゴールを明確にしておく必要があります。
- 相手のビジネスモデルと現状のボトルネックを言語化しておく
- どの課題に焦点を当てるかを1つに絞る
- 商談のゴールを明確にして、会話を迷わせない
この段階で焦点が合っていれば、商談中のヒアリングや提案がスムーズになります。
商談中:話すより聴く
商談の場では、「どれだけ話すか」よりも「どれだけ相手に話してもらうか」が成果を左右します。課題や本音は、相手が安心して話せる環境でしか出てきません。
- 相手の言葉を遮らず、要約して返す(傾聴+確認)
- 「なぜ」「具体的に」「もう少し教えてください」を意識的に使う
- 提案は相手の言葉を引用して行うことで納得感を高める
一般的に、ヒアリング量と成約率は比例関係にあります。相手に十分話してもらうことが、提案の精度を決めます。
商談後:接点を切らさない
フォローを怠ると、せっかく築いた信頼が一気に薄れます。商談後は検討が続く状態を維持する意識が重要です。
- 商談終了後24時間以内に要点と次のステップをまとめて送る
- CRMで温度感・決裁プロセス・関係者を記録する
- 失注案件もリスト化し、数か月後に再提案のきっかけを作る
関係を切らさずに情報提供を続けていくことで、失注案件が再商談化する確率が高まります。
商談を仕組み化して成果を安定させるには
営業は個人のスキルや経験に左右されやすい仕事ですが、商談の流れを仕組みとして管理することで、成果のばらつきを減らし、再現性を高めることができます。
属人的なやり方に頼らず、商談プロセスを見える化して改善を重ねることが大切です。
商談のステータスを明確にする
商談を「感覚」で進めるのではなく、フェーズごとに管理することは、既に多くの企業で取り入れられています。
| 商談ステータス | 内容 | 次のアクション例 |
| 接点獲得 | 問い合わせ・紹介・架電などで初接触 | アポイント設定、情報収集 |
| ヒアリング完了 | 現状と課題の把握ができた状態 | 提案資料作成、見積もり準備 |
| 提案中 | 解決策を提示して検討中 | 懸念点のヒアリング、再提案 |
| クロージング | 契約条件・導入スケジュール調整 | 稟議資料や契約書の共有 |
| 受注・失注 | 結果確定後 | フォロー・再提案・分析 |
このように定義しておくことで、各商談がどの段階にあるかを誰でも把握できます。チームで管理している場合も、フェーズを共有するだけで情報連携がスムーズになります。
ただし注意したいのは、フェーズを細かく分けすぎないこと。入力作業が煩雑になったり、意味の薄いKPIが増えてしまうと、数字を追うこと自体が目的化し、現場のアクションが遅れます。
あくまで改善のための把握に留め、運用負荷とのバランスを取ることが大切です。
数値で見る ― 商談率・成約率を可視化
商談率や成約率は感覚ではなく、数値で現状を把握します。
- 接点→商談率
- 商談→提案率
- 提案→成約率
これらの数値を月単位で追いかけると、どの段階で歩留まりが起きているかが見えます。たとえば「商談数は多いが成約が少ない」場合、提案内容かクロージングの設計に課題があると判断できます。
改善サイクルを回す
管理の目的は、数字を眺めることではなく、改善の仮説を立てて検証することです。
- ボトルネックを特定する
- 改善仮説を立てる(例:ヒアリング項目を見直す)
- 実践し、結果を比較する
個人任せにせず、チームで改善を繰り返すことで、商談の質が安定していきます。
仕組み化のゴール
最終的な目的は、「誰が商談しても同じ水準で成果を出せる状態」を作ることです。スクリプトやテンプレートを用意し、商談記録を共有できる仕組みを整える。属人的な営業を脱し、プロセスで成果を出す体制に変えていくことが、安定的な成約率をつくります。
商談に関するよくある質問(FAQ)
最後に、商談の内容や流れに関する質問に回答します。
-
Q1. 商談は何回で決めるのが理想ですか?
-
A. 回数は目的によって異なります。一般的には、
1回目:課題の整理と方向性の合意
2回目:提案内容の確認
3回目:条件の調整・最終決定
という流れが基本です。無理に早く決めようとするよりも、意思決定に必要な情報が揃う順番を意識することが重要です。
-
初回商談で価格を提示してもいいですか?
-
見積もりが必要な商材では、課題や適用範囲が明確でない段階で金額を出すと、誤った印象を与えることがあります。そうした状況で提示を求められた場合は「現時点の想定条件では、おおよそ◯◯〜◯◯円程度です」と前提を添えて伝えると誤解を防げます。
-
決裁者が同席しない場合はどうすればいいですか?
-
まず、同席している担当者の役割を確認します。
「今回のお話は社内でどなたに共有いただく形になりそうですか?」 と聞くだけで、決裁フローを把握できます。そのうえで、決裁者が関心を持ちそうな視点(コスト・リスク・導入効果)を意識して資料を残すと、社内共有時に話が通りやすくなります。
-
商談で断られたら、もう連絡しないほうがいいですか?
-
断られた理由を具体的に確認することが大切です。「時期」「予算」「優先度」「競合」など、どの理由かによって再アプローチの時期が変わります。
「今回は時期の問題とのことでしたが、次回の見直しはいつ頃を予定されていますか?」と確認し、CRMにリマインドを設定しておけば、失注案件を再商談化できます。
-
オンライン商談と対面商談で注意点は違いますか?
-
基本の流れは同じですが、注意すべきポイントが異なります。
項目 オンライン 対面 見せ方 スライドを共有しながら要点をチャットで補足 ホワイトボードや資料を使って視覚的に整理 間の取り方 相手の反応が見えづらいので、話の区切りごとに質問を挟む 相手の表情を観察しながらテンポを調整 アジェンダ 事前共有が必須。冒頭1分で再確認 口頭共有でも成立しやすい 雑談 無理に入れず、本題後に軽く 移動や名刺交換時に自然に行う オンラインでは「見やすさ」と「タイムマネジメント」、対面では「空気感と距離感」が成果を分けます。
-
商談後の議事録はどこまで書くべき?
-
要点をまとめすぎず、相手との合意内容とToDoを明確に残すことが目的です。
記録すべき要素は次の4つ。
- 商談の目的
- 合意事項(決まったこと)
- 保留事項(未決事項)
- 次のアクション(誰が・いつまでに何をするか)
フォローメールと同時に共有すれば、認識のズレがなくなり、次の商談が格段にやりやすくなります。
まとめ/商談は理解・設計・継続して成果につなげる
商談は、話術や経験で決まるものではありません。相手を理解し、目的を設計し、関係を継続する。この3つを丁寧に積み重ねることで成果が安定します。
営業代行の現場でも、商談を「瞬間の会話」ではなく、「再現可能なプロセス」として捉えています。そのために必要なのは、
- 商談前に相手の状況とゴールを設計する
- 商談中に課題を引き出し、共に整理する
- 商談後も接点を切らさず、次の機会をつくる
この3点を仕組みとして回していけば、属人的な営業から脱却し、組織として成果を積み上げられます。
最終的に、商談とは売る場ではなく、相手と成果を共有する場。この視点を持つだけで、会話の質も、数字の安定性も大きく変わります。